
M&A-NEXUSsponsored by 株式会社キャリアラダー
このサイトは株式会社キャリアラダーをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
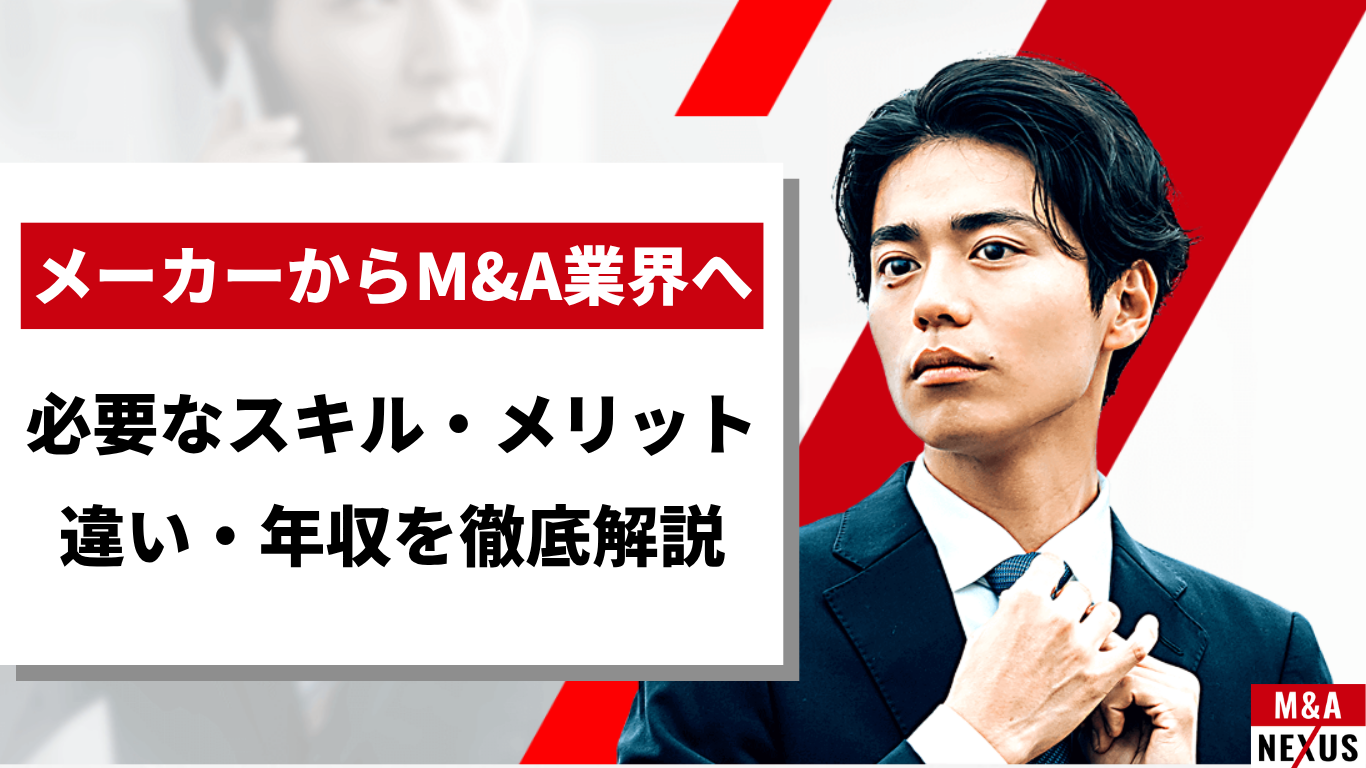
日本企業が関与したM&A取引は近年増加傾向を継続し、2024年の成約件数は4,700件と統計開始以来の最多を更新しました。市場が拡大している背景には、製造業を含む幅広い企業が事業ポートフォリオの再構築を進めていることがあります。半導体やEV関連の大型投資が相次ぐ一方で、収益性の低い事業を手放して成長領域へ資本を集中させる動きが盛んです。
製造業同士だけでなくIT・ヘルスケアといった異分野との協業案件も増え、案件サイズや業種の多様化が加速しています。こうした変化に合わせ、仲介会社やフィナンシャルアドバイザー各社はエンジニアリングやサプライチェーンの知見を持つ人材を積極的に採用し、製造現場を理解するアドバイザーの稼働率を高めようとしています。製造系出身者は原価計算や品質保証の仕組みを熟知しているため、デューデリジェンスでのリスク抽出やシナジー試算に直結しやすく、採用ニーズは今後も底堅く推移する見通しです。
※参照元:マールオンライン(https://www.marr.jp/menu/ma_statistics/ma_markettrend/entry/56991)
工場運営や製品開発に携わった経験を持つ人材は、工程管理・原価管理・品質管理といった実務を通じて「数値で課題を把握し改善案を提示する力」を身につけています。M&Aの世界では、買い手が得られる生産効率や共同開発効果を定量化して示す場面が多く、製造業で培った改善志向がそのまま武器になります。
また、製造業のバリューチェーンは取引先が多岐にわたり、部門横断で合意形成を取る文化が根づいています。こうした折衝スキルは、買収側・売却側・専門家チームなど利害関係者が入り乱れる案件運営で高く評価されます。さらに、設計図面・設備仕様・部品表など技術資料を読み解けるため、工場評価や設備投資判断に説得力を持たせることが可能です。
言い換えれば「現場を理解した経営視点」を持ち込める人材として重宝されるのがメーカー出身アドバイザーの強みです。
M&A仲介会社の給与体系は「固定給+成功報酬」が一般的です。製造業の年功序列型賃金と比べ、成果がインセンティブとして加算される比重が高く、担当案件の成約がダイレクトに年収へ反映されます。数字で評価される文化は、製造現場で生産指標や原価改善率を追ってきた人にとって納得感の高い仕組みと言えます。
また、昇格基準も案件実績が中心のため、社歴より成果がキャリアスピードを左右します。リーダーに昇格すると複数プロジェクトを束ねる立場となり、人員計画や収益管理に関わる機会が広がります。製造業では技術職から経営企画へ進む道が限定的なことも多いですが、M&A業界では案件を通じて財務・法務・事業戦略を横断的に学べるため、経営層に近いポジションへステップアップしやすい点が大きな魅力です。
製造業の実務では品質・コスト・納期を中心に考える傾向がありますが、M&Aでは企業全体の成長戦略を踏まえて資本配分を議論します。案件では、買い手が取得後に得る技術プラットフォームや販路拡大効果を示し、統合後の組織設計や設備投資計画まで検討します。
メーカー出身者は製造現場のボトルネックや投資回収期間を分析する能力が高く、買い手経営陣に具体的な改善ストーリーを描ける点で優位性があります。財務モデリングや契約法務を学ぶことで、技術と経営の言語を両方扱える人材へ進化し、事業会社の経営企画や投資ファンドのバリューアップ担当など選択肢が広がります。現場起点で培った改善マインドにガバナンスや資本戦略の視点が加わるため、長期的なキャリア拡張性が高いといえます。
案件の立ち上げ段階では、譲渡候補企業を選定し経営者へアプローチします。メーカー出身者は同業他社やサプライヤーとのつながり、展示会・商工会議所などで築いたネットワークを活かして有望案件を発掘できます。面談では事業承継や市場シェア拡大など経営課題を傾聴し、M&Aを実行した場合の製造ライン統合効果や研究開発効率化を示して提案します。
技術用語を咀嚼して財務的インパクトに変換できる点が信頼獲得の鍵であり、メーカー出身者はその橋渡し役として価値を発揮します。
基本合意締結後は、財務・税務・法務の専門家と連携しながら詳細調査を進めます。製造業特有の設備耐用年数や製造原価構造、品質保証体制をレビューし、買い手側の工場と統合した際のキャパシティ試算を行います。技術者同士のディスカッションをファシリテートし、専門家からの指摘事項を経営者へ平易な言葉で伝える通訳的役割も求められます。
最終契約の調整局面では、設備更新費用負担や環境規制対応コストなど製造特有の論点を盛り込み、双方が納得できる条件へ導きます。クロージング後は統合計画の進捗を確認し、想定シナジーが実現できているかモニタリングを行う場合もあります。
選考では、製造現場で達成した改善実績や新製品立上げ経験が定量・定性の両面で問われます。原価率の削減幅やライン稼働率の向上など具体的な数字を用いて成果を説明できると説得力が高まります。
また、M&A案件は半年以上の長期タスクであり、試行錯誤を続けて最終的に目標を実現する粘り強さが必要です。さらに、守秘義務契約や利益相反管理といったガバナンスへの意識が不可欠で、品質規格や安全基準を厳守してきた製造経験は倫理観の裏付けとして評価されます。
必須資格は設定されていませんが、簿記2級やビジネス会計検定を取得していると財務モデルの理解が進みやすく面接での評価が上がります。加えて、QC検定や技術士、プロジェクトマネジメント資格など、ものづくり領域で努力してきた証明があるとアドバイザーとしての説得力が強まります。
M&A関連ではビジネス実務法務検定やM&Aスペシャリスト試験の学習履歴があると、契約交渉フェーズの適応速度を示す材料になります。面接では学び続ける姿勢と技術的知見を経営判断へ翻訳する意思を示すことが重視されます。
メーカー(製造業)で培った、製品開発、生産管理、販売といった事業の根幹に関する知見は、M&Aの世界で高く評価されます。しかし、価値創造の考え方や業務の進め方は大きく異なります。
メーカーの価値創造が、優れた製品を開発・製造・販売する「良いモノづくり」にあるのに対し、M&Aの価値創造は、事業の売買を通じて、企業グループ全体の価値を最大化する「事業ポートフォリオの最適化」にあります。プロダクトではなく、事業そのものが評価の対象です。
メーカーの中心業務が、研究開発から調達、生産、販売、アフターサービスに至る一連の「事業プロセス」であるのに対し、M&Aの中心業務は、企業の価値評価(バリュエーション)、デューデリジェンス、交渉といった「取引プロセス」です。現場のオペレーションではなく、企業の所有権の移転を扱います。
メーカーの事業活動が、長期的な視点での研究開発や、安定した生産・販売といった「継続的な事業運営」である一方、M&Aの仕事は、数ヶ月から1年程度の期間でディールを完遂させる「短期集中のプロジェクト」です。特定のゴールに向け、集中的に業務を遂行します。
メーカーで求められる専門知識が、担当分野(技術、生産、品質管理、営業、マーケティングなど)に深く根差しているのに対し、M&Aでは、財務・会計・税務・法務といった、あらゆる業界に共通するコーポレートファイナンスの知識が基盤となります。
メーカー出身者ならではの「事業の解像度の高さ」は、M&Aの世界で強力な武器になります。その強みを活かし、ファイナンスという新たなスキルを掛け合わせることで、独自の価値を発揮できます。
あなたの最大の強みは、製品がどのように作られ、どのように顧客に届けられ、どう利益を生むのかという、事業のバリューチェーン全体を深く理解していることです。この「事業の解像度の高さ」は、M&A対象企業のビジネスモデルや競争優位性を本質的に理解する上で、財務情報だけを見ている他の候補者にはない、絶対的な優位性となります。
事業への深い理解を、M&Aの土俵で活かすためには、「経営の共通言語」であるファイナンスの知識が不可欠です。簿記や会計の基礎を学び、財務三表を読み解けるようになることは最低条件。その上で、企業価値評価(バリュエーション)の考え方を学び、事業の知見を数字に落とし込む力を養いましょう。
自身の経験を、事業の利益や価値向上にどう貢献したか、という視点で語り直します。「生産管理を担当」ではなく、「新たな生産方式を導入し、製造原価を〇%削減、営業利益率の〇%改善に貢献した」のように、具体的な数字を用いて、自身の介在価値をアピールすることが重要です。
一口にメーカーと言っても、業界や職種は様々です。自身の経験が、どのようなM&Aの領域(例:特定の業界特化チーム、事業再生ファンドなど)で評価されるのかを客観的に把握するために、専門エージェントへの相談は有効です。自身の強みを最大限に活かせるキャリアを共に模索しましょう。
面接では、事業会社の一員から、事業を動かす側へと視座が高まったことを示す必要があります。「自社の事業に携わる中で、個別の改善活動だけでなく、事業の売買や再編といったダイナミックな打ち手こそが、真の企業価値向上に繋がると感じた。メーカーで培った現場感覚を活かし、より大きな視点で企業の成長に貢献したい」といったストーリーで、キャリアの進化を語りましょう。
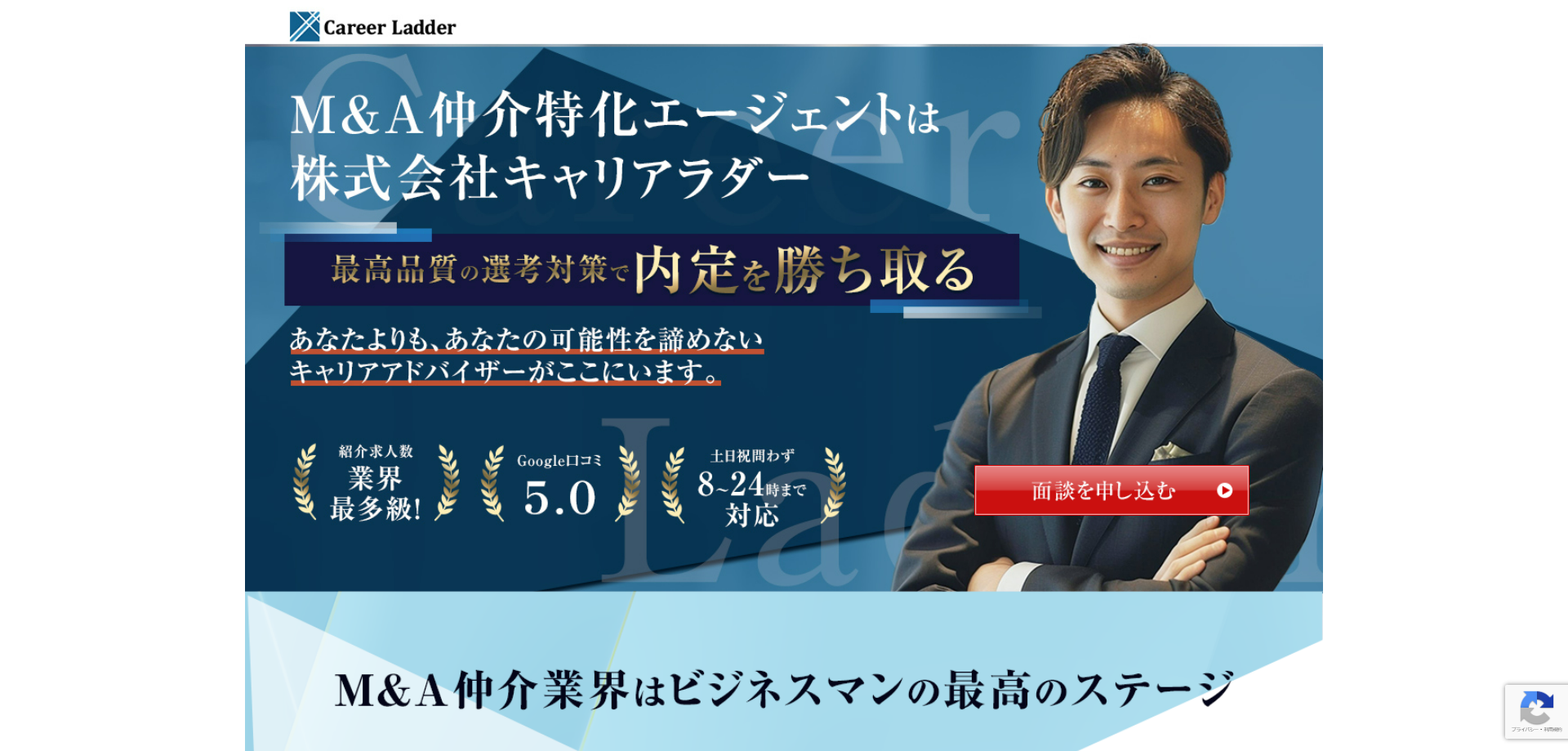
キャリアラダーはM&A仲介専門の転職エージェントとして、大手から独立系まで30社超の求人を取り扱っています。初回面談で年収希望や得意領域をヒアリングし、製造経験が活かせる案件比率や業務内容を具体的に提示します。その後、職務経歴書を業界フォーマットへ最適化し、応募企業のビジネスモデル分析レポートを共有します。書類選考通過後は想定質問集をもとに最適な答え方をすり合わせ、模擬面接で技術実績と経営視点をバランス良く語る練習を重ねます。
面談はオンライン・オフライン両方に対応し、土日や夜間の枠も確保して在職中の忙しい候補者を支援しています。内定後はオファーの条件調整や入社後の研修計画づくりをサポートし、定着後のキャリア相談も継続して受け付けています。メーカー出身者が専門用語と財務用語を両立して語れるようになるまで並走する姿勢が高い評価を得ています。
A:仲介会社の成果連動型インセンティブは案件規模と件数に応じて支給されます。固定給の伸びが限定的なメーカーと比較して、実績が収入へ還元される幅は大きいです。ただし、成果が出るまで時間がかかる場合もあるため、初年度は固定給部分をベースに生活設計を行い、インセンティブは余剰資金として管理する方が安心です。
A:製造工程や原価構造を理解していること自体が大きな強みです。面接では、その経験を活かして案件でどのような価値を提供できるか具体例を交えて説明すると好印象です。財務や法務の専門知識は入社後に研修や実務を通じて習得できる体制が整っています。
A:企業価値評価の基礎やM&A契約の概要を押さえておくと、入社後のキャッチアップが早くなります。製造業向けの統合型報告書やIR資料を読み、シナジーを数量化する訓練をしておくと面接でのアピールに直結します。
「できることは全部やりたい」
キャリアラダー代表インタビュー
M&A仲介転職支援の想いとは?

引用元:キャリアラダー公式サイト(https://careerladder.jp/)
平均30回以上の丁寧な面談サポート!
未経験でも安心して挑戦できる
M&A仲介業界特化型転職エージェント

引用元:キャリアラダー公式サイト(https://careerladder.jp/)
「ここまでやってくれるのか」と思うような充実のサポート内容が魅力。M&A業界に精通した専任アドバイザーがLINEでいつでも相談OK!未経験の不安も気軽に聞けて、内定まで伴走。内定まで週に1回程度の面談を行いながら、書類作成・自己分析・企業研究サポートや情報共有、模擬面接などを完全無料で行ってくれます。
内定獲得までの面談数は平均30回以上!金額面や入社時期など、候補者自身が伝えにくい給与や入社時期などの条件もプロが交渉してくれるので安心です。
サポート内容一覧